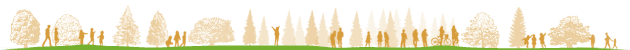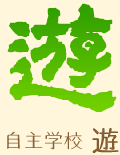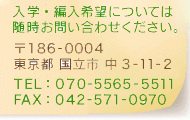遊は日々、成長し続けています。
|
「遊」は、1995年4月に誕生しました。最初は生徒ふたり、親、教師の小さな出発でした。2024年4月現在で、小学1年生から高校3年生までの子どもの数が33人、教師の数が19人になりました。また、さらにその周りにも「遊」を支え、応援してくださる大勢の輪ができています。 |
 |
教科書がない
|
子どもたちは授業の内容を絵や文章にしてノートにかきこんでいきます。一回のシリーズが終わると、世界で一冊しかない自分だけの教科書が仕上がります。何かの拍子に古いページに目がいくと、子どもたちは自分のかいた絵や文になつかしそうに見入って、朗読したり、思い出話をしたりします。他の子のかいたものも、みな細部に至るまで実によく覚えています。 |
 |
カリキュラムを作っていく
|
先行するさまざまな試みを参考にしながら、子どもの発達段階に合わせた教材を考えています。子どもたちがちょっとした会話の端々や遊び方の変化を通して、新しい興味の目覚め、心の成長ぶりを示してくれるのも、カリキュラム作りに役立てています。 |
テストがない
|
一人一人の理解の具合はよくわかっているし、子どもたちは各自のペースで意欲的に課題に取り組むので、テストの必要はないようです。 |
いわゆる「通知表」はない
|
子どもを数値では評価しません。 |
遊の授業から
小学1年生ある時の「漢字」
|
1年生の秋、漢字を始めた。まず「土」という字に取り組んだ。1日目は画用紙を横につなげてクレヨンで広い大地を書き、そこにそれぞれ好きな種をまく。2日目の天気は土砂降りの雨だった。画用紙を上にもつなげると「あめふり」の詩を口ずさみつつ、勢いにのって雨を降らせる。 |
小学3年生ある時の「家づくり」
|
遊の3年生は、エポック授業で「家づくり」をします。
はじめは、人にとっての住居の必要性をいっしょに考えます。「大昔に突然戻っちゃって夜になったらどこで寝ようか」「木の下じゃあ、けものがくるね」「やっばりほらあながいいよ」「水がいるよね、川が近くにないと」「食べ物のある森もなくちゃ」原始人気分の子ども達の想像は広がります。 |
中学1、2年生ある時の「歴史」
|
まず、二千年物差しを作る。紙を細く切って貼り合わせ、巻き尺を作る。一年を一ミリにすると二千年は二メートル。それに一世紀=十センチごとの目盛りを刻む。飛鳥、鎌倉・・・といった時代区分は、きれいに色分けをして示す。この物差しで計ると、...【続きをもっと読む】 |